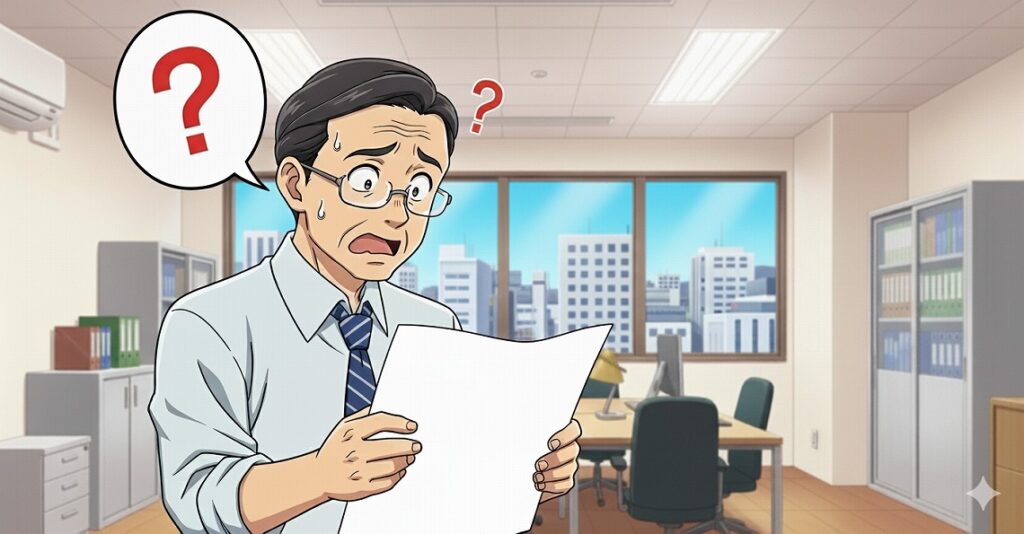店舗や事務所を貸し出す家主様、またはこれから不動産投資を考えている地主さんへ。今回は、**非常にトラブルが多く、しかも責任が家主様にある「用途変更申請」**について、お話ししたいと思います。この制度を知らない家主様や不動産会社の人が大変多いため、ぜひこの記事で正しい知識を身につけ、ご自身の資産を守ってください。
そもそも「用途変更」とは?
「用途変更」とは、既存の建物を異なる用途に変更することを指します。例えば、もともと事務所として使っていた建物を飲食店として貸し出す場合などがこれに該当します。特に、200平方メートル以上の建物を、類似の用途以外の「特殊建築物」に変更する場合は、建築基準法に基づく**「建築確認申請」が必要**になります。
建築確認申請が必要となるのは、新築時、増改築、大規模修繕、そしてこの「用途変更」の際です。
用途変更申請が「不要」なケースと「必要」なケース
- 200平方メートル未満の建物:用途変更の届出は基本的に不要です。例えば、一般的な戸建て住宅の面積は40~50坪(約130~165平方メートル)程度なので、多くの場合、届出は必要ありません。
- 類似業種への変更:ラーメン店から焼肉店のように、飲食店から飲食店といった類似の業種への変更は、用途変更の申請は不要です。
ただし、注意が必要です。2019年6月29日に建築基準法が緩和されるまでは、100平方メートル以上で用途変更が必要だったため、それ以前に建てられた小規模物件でも用途変更が必要な場合があります。
「特殊建築物」ってどんなもの?
「特殊建築物」は建築基準法で細かく分類されています。具体例を挙げると、以下の施設が該当します。
- 劇場、映画館、公会堂、集会場など(例:家族葬で使われる集会場)
- 病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など(例:グループホームは寄宿舎に分類)
- 学校、体育館など
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、飲食店、物品販売業を営む店舗など
- 倉庫
- 自動車車庫、自動車修理場など
これだけ聞いても分かりにくいかもしれません。さらに、児童福祉施設に該当するものも非常に多く、保育所、放課後デイサービス、児童発達支援センターなどが含まれます。老人デイサービスや有料老人ホームなども「児童保護施設等」に該当します。
こう考えると、戸建住宅と事務所以外は、人に貸す場合はすべて特殊建築物になると考えた方が良いかもしれません。つまり、200平方メートル未満か、類似業種への変更でない限りは、基本的にすべて用途変更申請が必要になると考えてください。
申請は「テナント」が、責任は「家主」が負う!
ここが最も重要なポイントです。
- 用途変更の確認申請を行うのは、実際にその建物を使用するテナントさんです。なぜなら、図面を作成する設計士や建築士に申請を依頼するのはテナントだからです。
- しかし、もし用途変更の確認申請を出さずに建物の使用を開始したり、違反があった場合の責任は、なんと「家主」が負うことになります。
テナントが申請するのに、責任は家主様にあるという、非常に理不尽に感じるかもしれませんが、これが現状なのです。
家主様がトラブルを避けるためにできること
このトラブルを防ぐためには、建物賃貸借契約書に「建物の用途変更の確認申請はテナントが行うものとする」という一文を明確に記載しておく必要があります。
しかし、この事実を知らない宅建業者(不動産会社)が非常に多いのが現状です。また、テナントさん自身も、これまでの出店が類似業種の居抜き店舗ばかりで用途変更が不要だったため、その必要性を知らないケースも少なくありません。さらに、内装業者の中にも、新築工事以外で確認申請を出すことが少ないため、用途変更に伴う申請の必要性を知らない人も多いのです。
ですが、責任と罰則はすべて家主様にあります。
まとめ
建物を貸し出す際には、テナントさんがどのような用途で、どのくらいの規模の店舗を借りるのかをしっかりと確認し、200平方メートル以上の特殊建築物への用途変更がある場合は、必ず賃貸借契約書にテナントの申請義務を明記しましょう。
ご自身の資産を守るためにも、細心の注意を払ってください。

 0120-925-104
0120-925-104