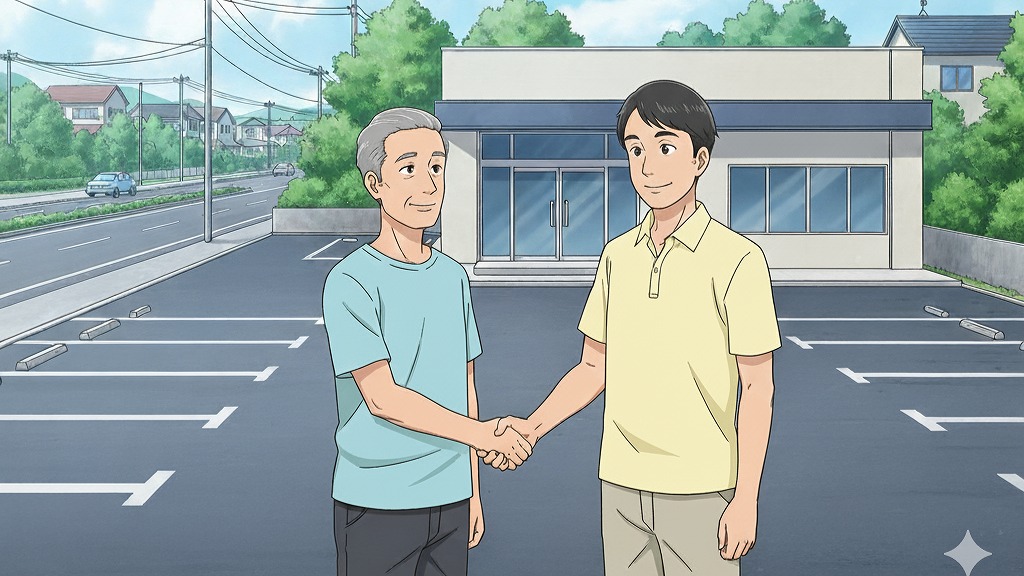土地活用を考えている地主様、建築会社から「隣地の方と一緒に土地を共同利用しませんか?」と提案されたことはありませんか?一見簡単そうに聞こえますが、実はそう簡単にはいかないのが実情です。
今回は、血縁関係のない他人同士、AさんとBさんの土地を共同で活用するという前提で、代表的な3つのパターンとその問題点、そして成功させる方法について見ていきましょう。
共同利用の3つのパターンと潜む問題
土地の共同利用には、大きく分けて3つのパターンがあります。
- 両方の土地にまたがる建物を共同で建てるパターン
- これは、AさんとBさんが共同で建築投資を行う方法です。
- 問題点: 投資金額の割合、修繕費、片方が売却する場合など、多くの問題が発生しやすいです。借地借家法の改正で定期借地権ができる前の1992年以前には見られた例ですが、親族間など特別な関係がない限り、基本的にこの方法は避けるべきとされています。
- Aさんの土地に建物を建て、Bさんの土地を駐車場として借りて共同利用するパターン
- ロードサイド店舗でよく見られる形式です。テナントはAさんと建物賃貸借契約(借家契約)を結び、Bさんとは駐車場契約を結びます。
- 最大のリスク: テナントもAさんも長期継続を前提に事業をスタートしますが、Bさんとの駐車場契約が不安定であることです。
- テナントとAさんの建物賃貸借契約は借地借家法で保護され、簡単に解約できません。
- しかし、Bさんとの駐車場契約は「土地の一時使用貸借」にあたり、借地借家法の適用外となります。
- つまり、Bさんからはいつでも中途解約が可能なのです。
- 将来の不確実性: 計画時はBさんも共同利用に賛成していても、将来Bさんが土地を売却したり、活用したり、競売になったり、相続で所有者が変わったりする可能性があります。実際に、駐車場が契約途中で利用できなくなり、閉店に追い込まれた店舗の例も知られているとのことです。
- AさんBさん両方の土地を事業用定期借地でテナントに貸すパターン
- これが、ベストな活用方法として推奨するパターンです。
- メリット:
- AさんBさんともに建築投資をする必要がなく、テナント名義の建物が建ちます。
- AさんBさん両方の土地が借地借家法の適用対象となり、どちらかが途中で事業を辞める心配がありません。土地が借地借家法で保護されるため、長期的な安定性が確保されます。
なぜベストな方法が普及しないのか?
残念ながら、この「事業用定期借地」という共同利用の例はあまり多くありません。その理由は、建築会社が地主様から高額な工事を受注できないため、この方法を積極的に提案しないからだと言います。
しかし、これからは地主様自身が建築会社の提案を待つだけでなく、自ら土地活用について深く考える必要があります。特に共同利用の場合は、この事業用定期借地という方法を検討することで、様々な有効活用が考えられるとのことです。
土地活用は大きな決断です。隣地との共同利用を検討する際は、安易な選択をせず、専門家の意見も参考にしながら、ご自身の土地を最大限に活かせる方法を慎重に選ぶことが重要です。

 0120-925-104
0120-925-104