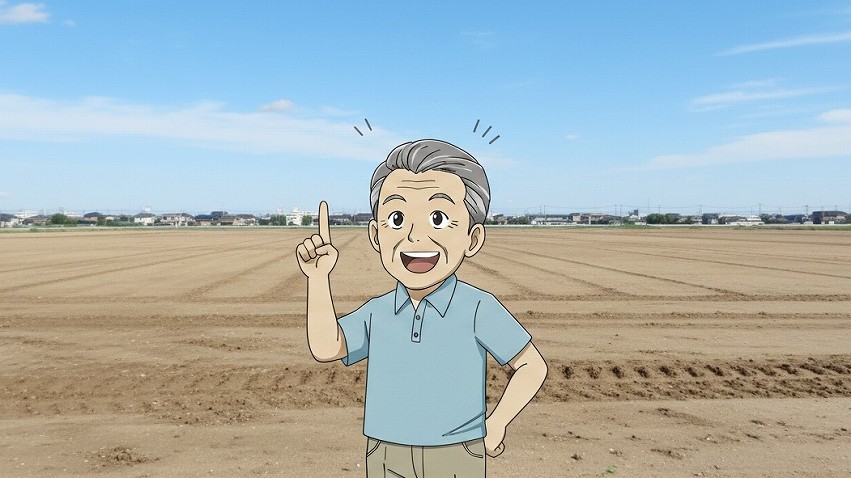今回は、ロードサイド店舗の土地活用を考える上で、絶対に押さえておきたい法律**「大店立地法(大規模小売店舗立地法)」**について深掘りしていきましょう。この法律、家主様にとっては非常に重要なんです!
大店立地法ってどんな法律?
大店立地法は、2000年6月1日に施行された比較的新しい法律です。それまでの「旧大店法」に代わって制定されました。
この法律の目的は、大規模な小売店舗が周辺の生活環境に与える影響(交通渋滞、騒音、廃棄物など)を考慮し、地域社会との調和を図ることです。大型店と地域住民が共存できるようなルールを定めているわけですね。
どんな店舗が対象になるの?
大店立地法の対象となるのは、**「大規模小売店舗」**と呼ばれる施設です。具体的には、建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートル(約300坪)を超える店舗がこれに該当します。
ここでいう「店舗面積」とは、商品を販売するための床面積、いわゆる「物販店舗」の売り場面積を指します。ポイントは、飲食店やサービス業(スポーツジムなど)の面積は、この1,000平方メートル(300坪)のカウントには含まれないということです。
届け出をするのは誰?必要な期間は?
大店立地法の届け出義務者は、建物の「設置者」、つまり**建物の所有者である「家主様」**です。テナントが届け出るわけではないので、家主様はこの点をしっかり理解しておく必要があります。
届け出にかかる期間ですが、通常は以下のようになります。
- 事前相談:約3ヶ月
- 届け出から意見聴取審議会:約8ヶ月
- 追加の意見聴取がある場合:プラス約3ヶ月
合計すると、基本的に許可されるまでに1年と少しの期間がかかると考えておきましょう。
旧大店法との大きな違いとは?
2000年に大店立地法ができるまでは、「旧大店法」という法律がありました。旧大店法では、500平方メートルを超える大型店が届け出の対象でした。
旧大店法と大店立地法の最大の違いは、目的にあります。
- 旧大店法: 中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することを目的とし、開店日や店舗面積、営業時間、休業日数などが調整されていました。この調整がつかず、出店を断念するケースが多々ありました。
- 大店立地法: 現在の法律では、調整がつかずに店舗が出店できなくなるという例はほとんどありません。その代わり、交通渋滞や騒音、廃棄物など、周辺の生活環境への配慮が求められます。
つまり、旧法が中小店舗保護を重視していたのに対し、現行法は地域環境との共存を重視していると言えますね。
家主様が特に注意すべきこと!
大店立地法に該当すると、駐車場台数の確保やガードマンの常駐義務など、運営コストの負担が増えることがあります。そのため、ドラッグストアや食品スーパーの中には、あえて売り場面積を300坪未満にして出店するケースも多いのです。
しかし、家主様はここで特に注意が必要です。 物販店舗と飲食店、サービス業などが混在する複合店舗を建築する際、物販の売り場面積を300坪未満に抑えて大店立地法の届け出を避ける場合があります。しかし、もし途中で飲食店やスポーツジムなどの非物販テナントが撤退してしまった場合、その空きスペースに新たに物販店舗を誘致しようとしても、大店立地法の届け出をしていなければそれができない可能性があります。
なぜなら、もし新しい物販テナントを入れることで、全体の物販店舗面積が1,000平方メートル(300坪)を超えてしまうと、法律上の問題が生じるからです。これは家主様にとって**「大きなマイナス」**になりかねません。
将来的なテナントの入れ替わりや活用を見据えると、無理に大店立地法にかからないようなプランにするよりも、最初から届け出をしておいた方が良い場合もあるのです。長期的な視点で、専門家と相談しながら計画を立てることが重要ですね。
この情報が、皆さんのロードサイド店舗での土地活用、特に家主様としての判断の一助となれば幸いです。
大店立地法はまるで**「交通整理の信号機」**のようなものだと感じた方もいるかもしれませんね。旧大店法が個々の車の出発を制限する(中小店舗保護)信号だったとすれば、大店立地法は、交通量全体(店舗の環境負荷)をスムーズにし、地域との流れを円滑にするための(渋滞や騒音を抑制する)信号へと変わった、と考えると、その違いがより明確になるのではないでしょうか。

 0120-925-104
0120-925-104